6月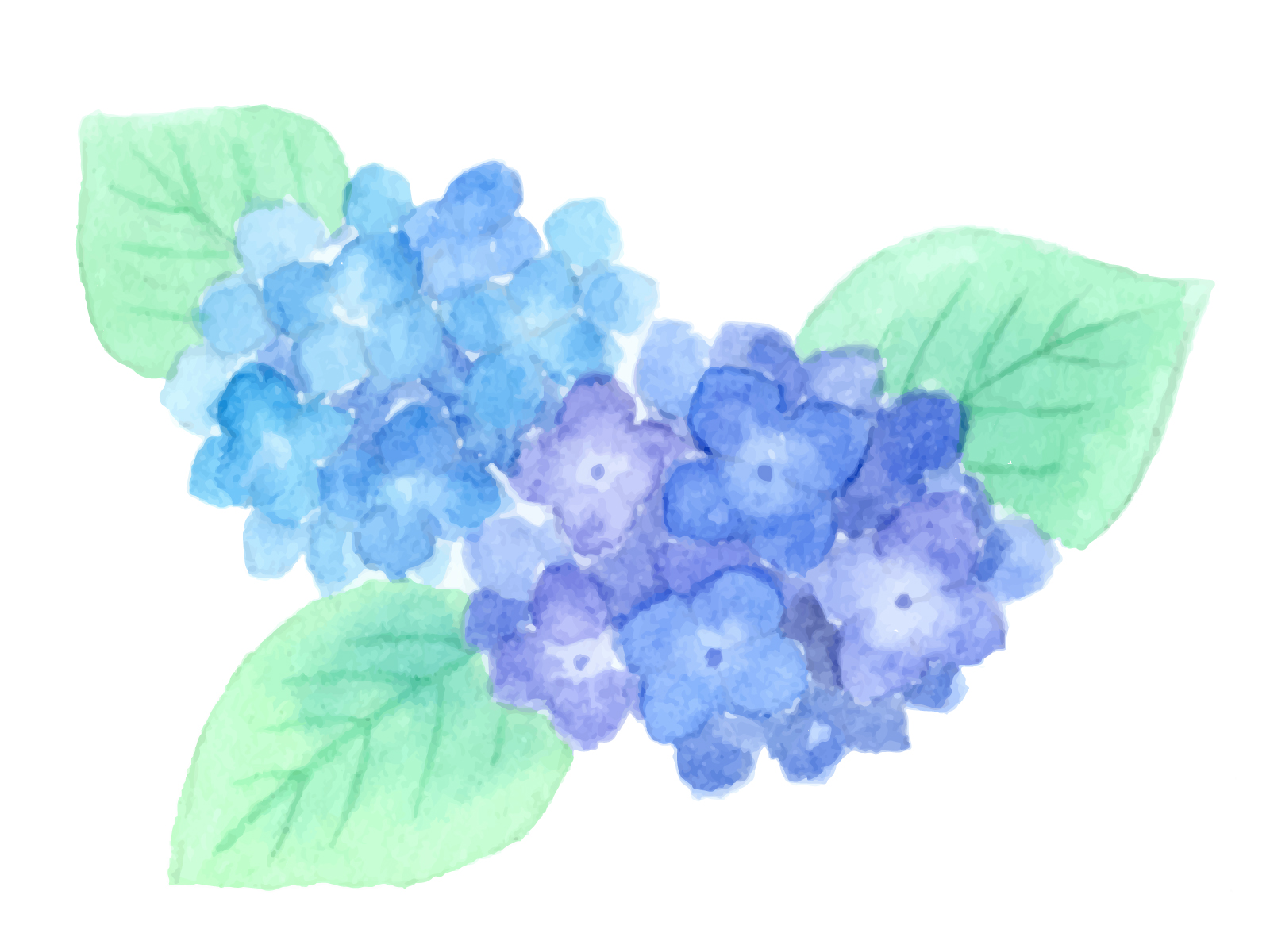
入職2年目の看護師です。私の看護体験をお話したいと思います。
私の働いている精神科急性期治療病棟では、10代~80代の幅広い年齢層の患者さんが入院しています。一人の患者さんは、入院当初不安感が強く幻覚におびえて何度も「怖い怖い」と訴えており、意思疎通をとることも難しい状態でした。しかし、治療をしていくうちにだんだんと他の患者さんとコミュニケーションがとれるようになり、入院時とはまるで別人のような笑顔で、手を振り退院されました。その姿を見て、精神科医療の大切さを改めて学ぶことができました。また、うつ病で不安症状がある患者さんとの関わりでは、不眠や不安症状が続き、薬を服用する事にも不安を訴えていました。看護者には、不安の原因となる気持ちを表出する事はなかった為、勤務の時は担当ではなくても、常に患者さんのもとへ行き挨拶をしたり、眠れないことに対しての思いを聞いたりしていました。ある時、私が休み明けで出勤した時に「待っていたよー話を聞いてもらいたくて」と声を掛けてくださいました。「いつも話を聞いてくれてありがとうね」と言われ、その患者さんにとって安心して話ができる存在になれたと感じた瞬間でした。患者さんとのかかわり方はお一人おひとり違う為、看護していく中で「これで良かったのかな」と不安になることも多く、振り返る事がたくさんあります。その中で、この患者さんからの言葉はとても嬉しい気持ちで一杯になり、自信にも繋がりました。これからも、一人ひとりの患者さんに寄り添える看護師に、成長していきたいと思います。


全1件中 1件を表示(1ページあたり20を表示)